「あたりまえ」とは、分かりきったことや言うまでもないことという意味。普通のこと過ぎて疑いもしない常識。そんな感じでしょうか。
でも国や文化が違えば、そのあたりまえは全然通じない、あるいは非常識に変わることもあるのが、異文化のおもしろさ。
現代の日本で生活する日本人からしたら、「なんだそれ?」な世界のあたりまえな価値観や考え方、物事の捉え方がたくさん書かれた本がこの「開幕!世界あたりまえ会議」なんです。
本の紹介
5つのテーマで世界の「あたりまえ」を紹介している本です。
・男女についてのあたりまえ
・人生についてのあたりまえ
・コミュニケーションについてのあたりまえ
・身の回りのあたりまえ
・生きるためのあたりまえ
の5つです。
全部で83の世界のあたりまえが載ってます。
世界のあたりまえに対して、”日本人からしたら、、、”の一言が添えられていて、その一言が「そうそう、ホントそうだよなぁ」と共感できる感想が書かれています。
知らなかった「あたりまえ」
1つ目:一妻多夫(チベット)
この本では、チベットの一妻多夫の例が挙がっています。
この「一妻多夫」の言葉自体は知っていました。一夫多妻に比べると一妻多夫の習慣がある地域は少なく珍しい習慣ということも知っていました。
が、このチベットの一妻多夫は兄弟で一人の女性を共有する、一妻多夫なんです。
なんとなく一夫多妻のイメージで男性は他人同士だとばかり思っていたのですが、兄弟同士のパターンもあるとは知りませんでした。
長男の結婚式に、弟たちも参加したあとは一緒に暮らし、妻を共有するとのこと。子どもが生まれた場合、子どもの父親は長男であり、弟たちは自分の子を持つことはできず、財産分与もありません。そのため、ある程度財産ができたら弟たちは自分だけの妻と結婚し、家を出ていくようです。
この地域の男性は交易でシルクロードを旅したり、遊牧で長期間家を空けることもあるとのこと。確かに夫が2人以上いてくれたら、1人が家を空けても、農作物の世話など男手が必要なときでも安心なので、非常に効率的ですね。
すごい仕組み!と思ったけど、この地域ならではの生活に合った習慣なんですね。
2つ目:独身男女には罰があたえられる(ドイツ北部・ロシア[マスレニツァのお祭り])
ドイツ北部には、30歳の独身男女は街の大聖堂のお掃除をするという罰があるとのこと。未婚の異性からキスしてもらうまでお掃除を続けるようです。罰といってもにぎやかで楽しい風習とのこと。
ロシアのマスレニツァのお祭りにある風習では、前回のお祭りから1年間結婚しなかった男女は、祭りの間中木材などで作った重い枷を首や足につけて歩かされる。お金を払うかごちそうを振る舞うことで、枷を外してもらえるようです。
それぞれの国全土で行われている「あたりまえ」ではないにせよ、すごい「あたりまえ」ですね。
なぜ独身者なのかというと早く結婚しなさいという圧力や社会の一員としての責任を果たしていないための罰ということなんだそうです。
昨今の日本では、結婚に関することを質問することがタブーな雰囲気ですから、独身者は社会的責任を果たしていないなんて言っちゃったら大炎上しかねないですが。
昔からの「あたりまえ」として地元の人には受け入れられているんですね。罰とは言いつつも、それが出会いの場にもなっているようですので、結婚のきっかけに繋がっているのかもしれませんね。
3つ目:南が上になっている世界地図(オーストラリア)
以前、日本が真ん中の世界地図を描いたら、海外で笑われてしまったという体験談を読んだことがありました。それまで日本が真ん中の世界地図がおかしいと思ったこともありませんでしたが、社会の授業で時差の勉強をしたときに、そのときはこういうものだと思ったんですが、分かりづらいなとうっすら感じたんです。なぜ分かりづらいと感じたのかその時はうまく言葉にできなかったのですが、大人になった今思うのは、経度0度のロンドンが真ん中にあり、その右側が東経、左側が西経とした地図を使ったほうが分かりやすかったのではないかな、ということです。
世界の人が日本が真ん中に書かれている世界地図を使っているわけないのに、ずーっとその世界地図しか見たことがなかったから、疑いもしなかったんです。
自国が真ん中に書かれた地図を使ってる国って日本だけなのかな、まるで世界の中心は日本だと言わんばかりのようで恥ずかしいかも、、、
と思っていたらまさか南半球が上の地図があるとは!!そして当然のようにオーストラリアが真ん中!
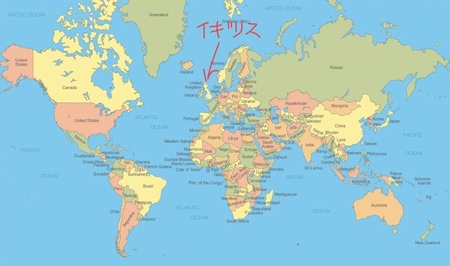
↑こちらの方がいろいろな国の世界地図を載せてくださってるのですが、本当多種多様ですね。
自国を真ん中に配置して世界をみてるのは日本だけではなかったんですね。
本では、江戸時代の江戸の地図は、天皇がいる西が上だったとのことですので、どこを上にするかは時代や考え方でこんなにも違うものなのですね。
感想
5つのテーマごとに、世界各地の「あたりまえ」が紹介されているのですが、自分が興味をもつテーマがきっとあると思います。
私の場合は、”第1部 男と女についてのあたりまえ会議”や”第2部 人生についてのあたりまえ会議”がとても興味深いあたりまえで溢れていました。
独身者に関するあたりまえを紹介しましたが、他にも死者同士だったり動物とだったり、神様とだったり、もう世界にはいろいろな結婚があって驚きです。
航空運賃は体重で決まる航空会社があれば、子供料金は年齢ではなく身長で決まる鉄道会社など。なにをもって公平とするか、なにを重視するのかでこんなところにも違いが現れるんですね。
この本を読み終えて、私は結婚に関することや身の回りに関する世界のあたりまえが、とても興味深いと感じました。ですが反対に、対立した場合の解決法や食事に関する議題にはそれほど興味がなかったことに気づきました。もしかしたら、その興味深いと感じる議題こそが、私の中で「これってこういうものだよね」というあたりまえで凝り固まった考え方の部分なのかもしれません。
この本を読んで、みなさんもどんな議題に興味を持ちなぜそう思ったのかを考えてみると楽しいと思います。
こんな人にオススメ
日本人の一般的な感覚からすると、「え?なにそれ!」な世界のあたりまえがたくさん載っているおもしろい本です。
見開き左ページの半分は、議題のイラストが描かれており文章量は多くないのですぐ読みきれます。
・雑学が好きな方
・「日本ではありえない」なエピソードを探している方
・異文化に興味のある方
にぜひオススメですよ。
異文化理解や同じジャンルの本が好きな方には、以前紹介した↓こちらの本も合わせてオススメです。
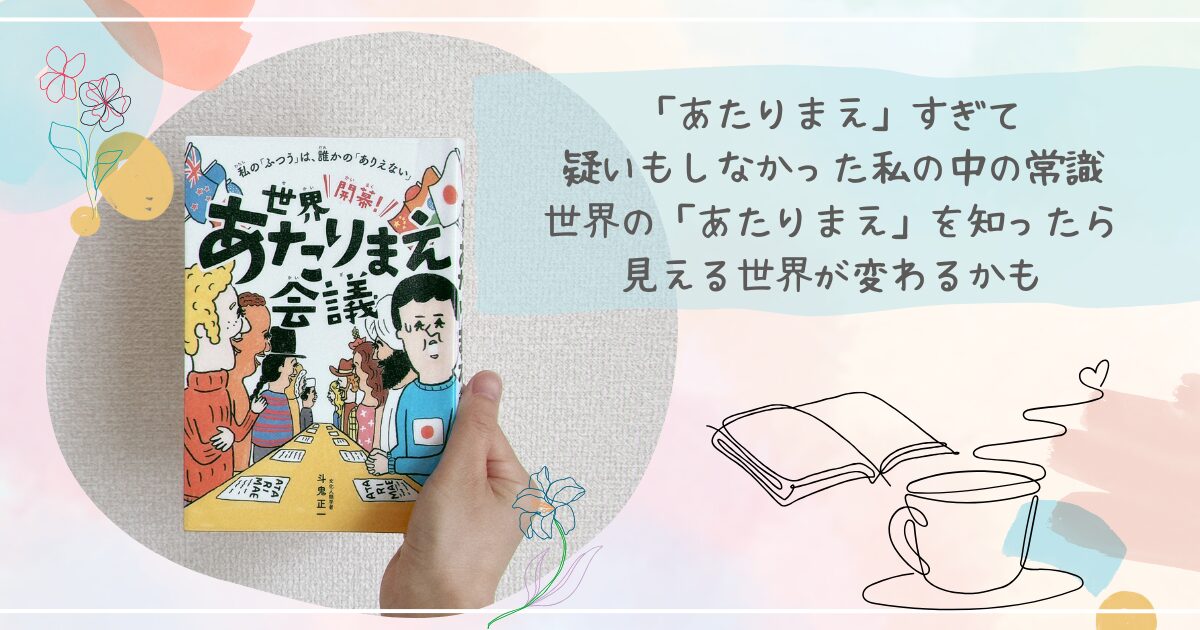



コメント