本の紹介
UAE人の男性と結婚し、UAEでの生活やアラブ社会の習慣などが紹介されたエッセイです。この本が出版されたのは2013年で、その時すでに結婚して20年ほどと本に書かれています。
メルマガで執筆し、書き溜めたものをこの本にまとめたものとなっています。各章の中の節の終わりにいつ書かれた記事なのかが書いてあります。
・プロローグ
・第一章 灼熱との闘い
夏の盛り
こわーい停電の話
砂漠の国に雨が降ると
・第二章 アラブの女性たち
娘について思うこと
ベールのこちら側
ある結婚式の情景
おんなの生活
・第三章 超自然現象とのつきあい
モバイルのゆくえ
吹雪の夜
・第四章 イスラームのはなし
ラマダーン前夜
喜捨の心得
ラマダーン真剣勝負
・第五章 湾岸アラブで子育て
砂漠のキャンプ
サプライズ
遅れた新学期
・第六章 激変するUAE
ザーイド大統領の功績
砂に願いを
偉人の思い出
四十年の歩み
ちょっとした思い出
祖母のはなし(第八回「文芸思潮」エッセイ賞受賞作)
エピローグ
読むきっかけと感想
日本の夏が猛暑から酷暑へと移りゆく8月。朝起きたときから気温は高く、何をするにも暑くてやる気が出ない毎日を過ごしていたときのこと。
最高気温40度でこんなにも大変なのに、もっと暑い国に住む人達はどうしているのだろうか?
と疑問に思ったのです。暑い国=中東と単純な考えから、この本に出会いました。
まさに最初の「灼熱との闘い」から、夏の大変さが伝わってきます。
自宅のサンルームの暑さをなんとかしようと、カーテンをつけるべく奮闘するハムダさん。しかしカーテンを固定しようにも、暑さでグルーガンは溶け失敗とのこと。日本では夏の屋外で溶けてしまうことはあっても、屋内ではさすがになさそう。おそるべしUAEの夏。
また、デーツを育てる記述のところでは、デーツ用に水を購入する人もいるとのことでした。生活用水には脱塩グレードの低い水を使っているという説明を見た時、やはり水が豊富ではないため、海水を使っているんだなと思いました。
ただ暑さだけの心配をすればいいということもなく、雨が降れば今度は雨漏りの心配もあるようで。
家だけでなく前年に建てた新しい学校ですら雨漏りをするそうで、まったくもって雨に対応する作りではないようです。
砂漠のイメージが強く一年中乾燥した国のイメージがあるUAEですが、雨が降るときもあるのですね。
雨がほとんど降らないため、雨が降ったら授業はそっちのけで、生徒たちは外に出て雨に打たれに行ってしまうと書かれていて驚きでした。日本人からしたら雨なんて何も特別なものではないけど、UAEの人たちからしたら恵みの雨ということなのでしょうか。
その一方で、
日本では雷のときは頑丈な建物の中で安全を確保することも、
雨の日の運転は視界が悪くなることやブレーキの効きが晴れている日とは違うことは常識。
洪水が発生したら車は水没することも考えて行動します。
でも雨がほとんど降らないUAEではその常識はなく、雨や洪水による事故が多発するそうです。
また気温の低下に対応する服も暖房器具もないとのことです。
この記載は2007年に書かれたものなので、現在のUAEがどうなのかはわかりません。でも↓このような投稿をされている方がいるので、雨への住環境はそんなに変わっていないのかもしれませんね。

UAEの人にとっての雨は、私たち日本人からすると暑さなのではないかと感じました。
日本も近年夏はどんどん暑さが増していて、熱中症警戒アラートや暑さ指数が毎日テレビなどで呼びかけられ不要不急の外出は避けることを推奨されています。
私が子供の頃の20年〜30年前も夏は暑かったけど、こんなに厳しい暑さではありませんでした。
ハムダさんが本の中で、
多くの人は、生きてきた中で得た習慣や常識が絶対的なものとして生きていくのかもしれない
とおっしゃっています。
今年の夏も、連日暑さによる被害のニュースが報道されていました。
猛暑で窓ガラスが割れた、雨が降らず気温も高いため農作物がうまく育たないなど。
だから、”ハムダさん、カーテンをつけるの大変ね”
“デーツを育てるのに水を買ってくるなんて砂漠は大変ね”
などと暑さによる大変さは
決してよその国のことではなくなってきているように感じます。
もちろん、海水から真水を作るなんて素人が言うほど簡単ではないことも、そんなことずっと前から考えて取り組んでるすばらしい技術者がいるであろうことも百も承知です。
ただ急速にかわりゆく日本の夏を乗り切っていくには、
ずっと昔から暑さとともに生きてきた人たちの知恵や常識が役に立ち、
私達日本人が学べることがあるのではないかと思える章でした。
初めて知ったこと
ラマダンの準備にたくさんの労力が必要ということです。
ムスリムではない私もラマダンは知っています。
ラマダンの間は、日の出から日没までの間飲食を断つこと。
断食を通して飢えに苦しむ人々への理解や共感、
それと同時に、食事にありつけることへの感謝を改めて感じる行為であること。
妊婦や病人、子供などは断食を免除されることなど、
しっていた
でも、この『アラブからこんにちは』を読んでラマダンはそれだけじゃなーーい!!
とハムダさんに言われたような気がしました。
なんでも、イード祭と呼ばれるラマダンが終わったことを祝うお祭りがあるのだそうです。
なるほどたしかに、約1ヶ月もの間、日中は断食を行っているわけですから
やり遂げたあとはお祝いもしたくなりますね。
ただ、その祭りは新しい服でお祝いするそうで、
その服はどれもオーダーメイドなのだそう。
そのためハムダさんは自分と娘たちの分の布を買い、それをもって今度は仕立て屋へ行き刺繍やらビーズやらの飾りを決め注文したのだそう。それもどの人もみな、同じように準備をするわけだからよく念を押しておかないと期日までに仕上げてもらえないなんてこともあるようで。
柄の組み合わせやら糸の色など、さらには流行にあったデザインであることも考えながらです。
しかも、用意する服は
ドレスとドレスの上に着るアバヤと頭部を覆うシェーラが必要とのことですから
読んでいるだけでも相当な労力だということが伝わってきます。
また、ラマダンの期間中は人が家に訪問する機会が増えるため
家の中を掃除や場合によっては整備をするなどの準備もあるようです。
ラマダンの間、日中は飲食を断つわけですから
それらを済ませておくことで、空腹なのか修理やら大変な場所の掃除を
しなくて済むようにという意味もあるわけですね。
ラマダンのことは知っていても
そのために日常でどんなことがなされているのかは
全く知らなかったので、どこを読んでも発見がありました。
一体ハムダさんは、結婚していつぐらいから
それができるようになったんだでしょうか。
知らない人からしたら
ただの体を覆う黒い布に見えるけど、
黒にもバリエーションがあってなおかつ
袖や襟のシルエットや装飾を含めたらそれはもう無限に組み合わせがあるわけです。
結婚した嫁を一族の女性みんなで世話をする習慣がアラブには
あるようですが、そのときに教わったのでしょうか?
それにしても、すぐに身につくほど簡単なことではないことでしょう。
こんなかたにおすすめ
ハムダなおこさんが暮らすUAEでのことが書かれていますので
アラブの生活に興味がある方
におすすめです。
天候やアラブ社会の習慣や考え方、おもてなしの仕方や学校や食事など
日々の暮らしのことがたくさん書かれています。
また、国際結婚って実際どうなの?
という方にもおすすめです。
異国へ嫁ぐ不安や、慣れないアラブの習慣にとまどったり憤ったり。
それでも「それがどうした」と乗り越えてきたハムダさんの強メンタルは
今、国際結婚を考えている人や実際に国際結婚で心が
折れそうな人は絶対読んでほしいです。
また、服装も男女の交際も一人で外を出歩くことも
自由であった自分の娘時代と、
その真逆の社会のUAEで育つ娘たちをみて
「これでいいのだろうか」と悩んだり、
その数年後に書かれた章では「あぁ、大丈夫なんだ」と安心したり。
自分が生まれ育った国とは違う国で子育てをする人は
きっとこういう経験をしてるんだろうなと感じました。
異国での子育てに、経験者の話が聞きたいという方は
読むとなにかヒントになるのではないでしょうか。
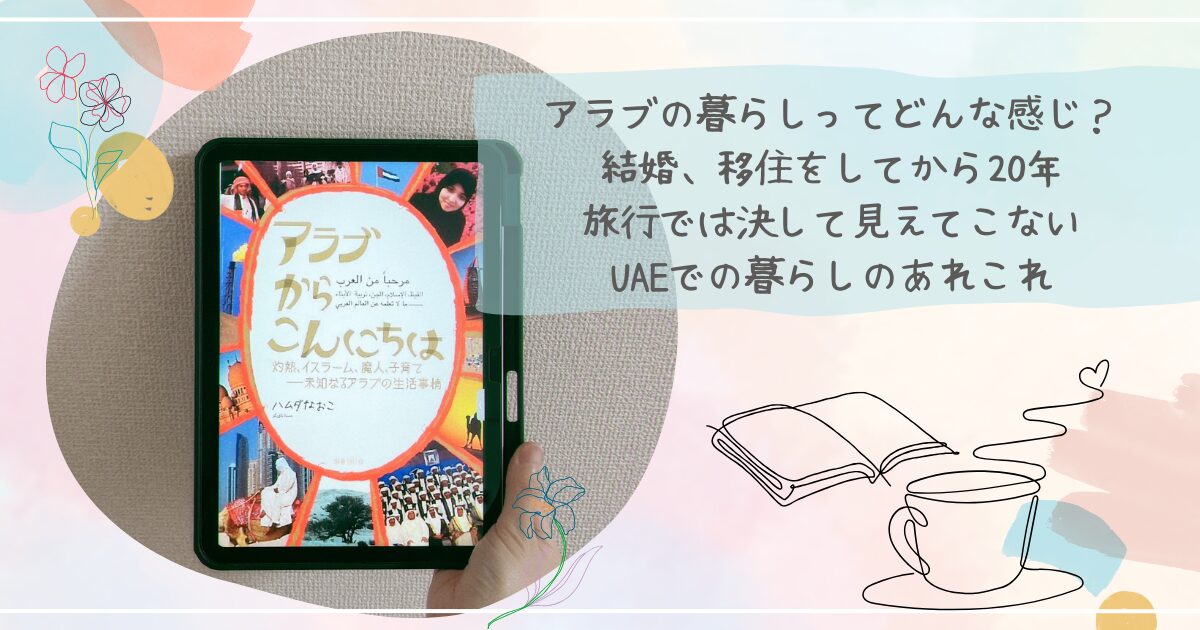


コメント